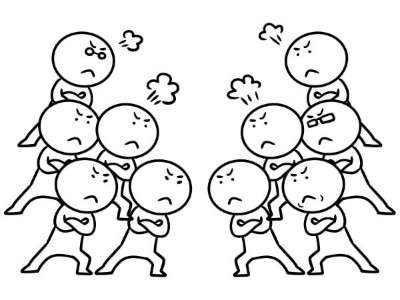2026年2月16日
日本建築-飛鳥・奈良(神社)
時代背景 天皇中心の国作り 645年に始まる「大化の改新」の流れを汲み、天武天皇は強力な軍事政権の樹立を図りました。律令制度の整備や中央集権化を進め、地方豪族の独立性を抑えます。 大化の改新:天皇中心の国作りを目指した一連の改革 その際に彼が利用したのは、「神道」でした。「神道」を国教として定め、神社を統一的に管理することで、天皇の威光と神格化を図ったのです。 この時代、すでに仏教も伝来していましたが、古代日本の政治権力は、神々との関係性を重んじることで正統性を獲得することができたという背景もあり、仏教で ...
ReadMore

2026年2月16日
日本建築-書院造・数奇屋
時代背景 接客空間の発展 信長・秀吉の時代を経て、戦国の混迷を抜け出すと、軍事ではなく、接客空間が求められるようになりました。 書院造 そして試行錯誤の末、「書院造」という一つの型が完成します。主に、城郭や寺院・武家の邸宅などの厳格な建物で用いられました。 風書院 ただ、形式化の一方で、その枠をあえて脱線する、遊び心に富んだ邸宅建築も表れました。数奇な人に造られた書院ということで、数奇屋風書院造と言われます。しかし、正式な建築には相応しくない格好であったため、主に山荘などで用いられました。 造形 建物の顔 ...
ReadMore

2026年2月16日
西洋建築-ビザンティン
背景 首都『コンスタンティノポリス』の誕生 330年、コンスタンティヌス大帝は、ローマ帝国の首都をギリシャの都市ビザンティウムに遷都します。その後、この都市はコンスタンティノポリスと名を改めました。 ビザンティウムに遷都したのは、ローマ帝国が内部の政治的・経済的・軍事的な問題や外敵の侵攻に直面していたためです。東方からの侵攻に備えるために、軍事上の要地でもあったこの地が選ばれました。 西洋社会の東西分裂 395年には、帝国は東西に分裂。ローマを首都とする西ローマ帝国、コンスタンティノポリスを首都とする東ロ ...
ReadMore

2026年2月16日
西洋建築-初期キリスト
背景 キリスト教の公認 キリスト教徒は当初、ローマ帝国によって迫害を受けていました。しかし313年に発布されたミラノ勅令*によって、これまでローマ帝国から弾圧を受けていたキリスト教が公認されます。 ミラノ勅令:4世紀初頭のローマ皇帝コンスタンティヌス帝によって発布された勅令で、キリスト教を公認するものでした。この勅令によって、キリスト教徒は迫害から解放され、徐々にローマ帝国内での信仰の自由が広がっていくのでした。 これによって、それまで地下に潜っていたキリスト教は、ローマ帝国の国教として華々しい役割を担う ...
ReadMore

2026年2月16日
日本建築-飛鳥・奈良(寺院)
時代背景 仏教の伝来 六世紀半ば頃、仏教が百済から日本に伝来*しました。その教えが持ち込まれると同時に、それを体現する場として寺院建築が必要になり、それに由来して仏教建築の新技術が持ち込まれます。 聖明(百済の王子)は、日本の皇室との外交関係を深めるために、日本に渡来し仏教を伝えたとされています。 仏教を受け入れるか、拒否するか ただ、仏教は満場一致で受け入れられた訳ではありませんでした。いわゆる、「排仏派」と「崇仏派」に分かれます。 国際情勢に明るい蘇我氏は賛成 主に「崇仏」を主張したのは、渡来人勢力と ...
ReadMore
前の様式
背景
行き過ぎた人間中心主義
ルネサンス文化を特色付けたものは人間性の再発見でした。そして、この人間性の範は古代に求められます。それゆえ人間の有限性を前提する筈でした。しかし、ルネサンス人は人間の有限性を忘れたかのように振る舞います。それはキリスト教においてさえ例外ではありませんでした。そしてこのような情勢に対する不満こそ、やがて来る宗教改革へと繋がって行くのです。
宗教改革の勃発
宗教改革の先駆けとなったのは、マルティン・ルターです。彼は「95ヶ条の論題」を掲げ、贖罪状の販売などの不正や教皇の権威主義を批判しました。
95ヶ条の論題:マルティン・ルターが1517年10月31日に公表した論文。教会が贖罪状の販売を行っていることについて批判し、キリスト教の教理に基づいた信仰に重点を置くことを主張しました。また、聖書中心主義を唱え、教皇の権威主義も批判します。この論文は当時のドイツ社会において大きな反響を呼び、ルターは教皇庁から異端者と宣言されるなどの迫害を受けましたが、一方で支持者も獲得し、プロテスタント宗教の成立につながっていきました。
ルターに続く宗教改革者は、ジャン・カルヴァンです。彼はルターと同様に、教会の腐敗や教皇の権威主義に反対し、聖書中心主義や信仰義認論を重視しました。また、神の絶対的な主権や予定説を唱えたことで有名です。
①神の絶対的な主権:人間の罪は神に対する背信であり、罪を赦す権限は神のみにあるという考え方②神があらかじめ人々の救済を決めているという考え方
その他の宗教改革者としては、ヘンリー8世も有名です。
ヘンリー8世が登場する記事》建築-イギリス・ルネサンス
宗教改革に対抗
幸いにも、教皇庁はこれらの宗教改革のおかげで自己反省の機会を得ました。教会の改革やカトリック教徒の信仰深化を目指して、内部改革が進められます。1545年から1563年にかけて、教皇パウルス3世の主導で開催されたトリエント公会議では、教義の確立や聖務の改革、司祭養成の充実、カトリック教会の教会法の体系化などが行われ、また教義上の論争や聖務の問題、教会内部の腐敗など、多岐にわたる改革課題に取り組みました。
特徴
相反するキリスト教とルネサンスの精神
キリスト教建築とルネサンス建築には、最初から相容れないものがありました。キリスト教建築は宗教的精神を必要としていたにも関わらず、ルネサンスの精神はそれと対照に理性的な性格を有していたからです。
そのため、バロックはルネサンス的古典を否定し、キリスト教的古典を目指すことを自らの使命としました。かくして、芸術表現は静けさから激しさへと移るのです。
造形・表現
反宗教改革の中心となった教皇は、自らの強大な権威や力を芸術表現によって示すことを求めました。そのためこの時代の様式は、分かりやすい・伝わりやすいという性格を有することになります。
感覚的な効果に訴えかける
曲線・装飾・透視図法的錯覚などを駆使して、見る人を惹きつけます。色・形・大きさなど、どれを取っても派手好みです。
豪華な装飾
イタリアバロック建築のファサードは、しばしば豪華な装飾が施されています。その多くは、宗教的なシンボルや聖書の物語などの象徴的な意味合いを持っています。
壁面に豊富な彫刻や装飾を施すことも特徴の一つです。
楕円形の平面を採用
バロックにおいては、ルネサンス時代の端正な形よりも、楕円の平面・捻じれ柱のような曲線・歪んだ形・動きのある形が好まれました。しかし、それは古典の権威に対する反抗ではなく、決まり切った単純な形を避けようという試みでした。整合性よりも逸脱に美を見出したのです。その結果、バロックは合理的な古典主義とは対極にあるものとして位置付けられることになりました。
楕円形には、儀式性の高い集中堂式と集会に強いバシリカ式との両取りという側面もありました。儀式的な空間と収容的役割を同時に併せ持つ効果が期待されたのです。
西洋建築入門|著.森田慶一|東京大学出版会
建築の歴史|編.西田雅嗣・矢ケ崎善太郎|学芸出版会
西洋建築様式史|著.熊倉洋介・末永航・etc|美術出版社
美術史〈西洋〉|編・中山公男 中森義宗|近藤出版社
次の様式
西洋建築史年表
日本建築史年表

2026年2月16日
西洋絵画−オランダ・バロック
舞台 オランダ 16世紀末、「プロテスタント」勢力の強かったフランドル地方の北部にて、「スペイン領からの独立」を果たした新教国、オランダが誕生しました。 背景 イタリアからオランダへ輸入 イタリア起源のバロックは、国境を超えてオランダにも広がりました。 プロテスタントの国 オランダ共和国として独立を果たし、「東インド会社等の国際貿易」により、目覚ましい「経済発展」を遂げたオランダは、その経済力を背景にオランダ独自の「市民文化」を繁栄させていました。 「プロテスタントの国」であったオランダでは、「教会よりも ...
ReadMore

2026年2月16日
西洋絵画−後期印象派
一般に、スーラ・セザンヌ・ゴーギャン・ゴッホの四天王を総称して後期印象派と呼ぶことが多いです。しかし、当ブログでは個人的な趣きもあって、新印象主義(スーラ)・セザンヌ・後期印象派(その他の画家)という風に細分化しています。 舞台 フランス 印象派に続き、フランスが芸術の中心地として君臨しています。 背景 時代背景は主に新印象主義と同じです。 印象派の乗り越え 時代の寵児であった印象派も、1886年には最後の展覧会を迎え、いよいよ批判と反省の対象として乗り越えられる存在になります。 物の形を犠牲にした印象派 ...
ReadMore

2026年2月16日
西洋絵画−ロマン主義
舞台 フランス 革命期から王政復古期にかけてのフランス。新古典主義が絵画の主導権を握っていた一方で、その「静的で厳粛な様式」は、人の心を真に動かす力に欠けていました。そんな中、絵画に再び「動き」を取り戻そうという流れが形成されます。 背景 ヨーロッパ各国の独立意識 「フランス革命」・「ナポレオンの侵略」という二つの事件をきっかけに、各国は「自我」に目覚めます。 古代ローマという西欧各国における「共通の祖先」から、「自国の歴史」・「風土」へと関心が移ったのです。 プロパガンダとしての絵画 ナポレオンの第一帝 ...
ReadMore

2026年2月16日
西洋絵画−フランス・ロココ
舞台 フランス 絵画史の中でも、特にロココは時代区分の難しい様式です。そもそもロココとバロックの区分を認めない説もあります。そのため当ブログでは、ロココの特徴が最も顕著に現れている、フランスで展開されたロココのみを取り扱います。 背景 絶対王政に陰りが見え始める 「太陽王ルイ14世」は、神から与えられた王権の行使者としての役割を演じることの出来た「最後の王」でした。 それというのも、1715年に彼が他界すると、その絶対王政にも陰りが見え始め、「貴族等の側近勢力が台頭」して来たからです。 太陽王からの開放 ...
ReadMore

2026年2月16日