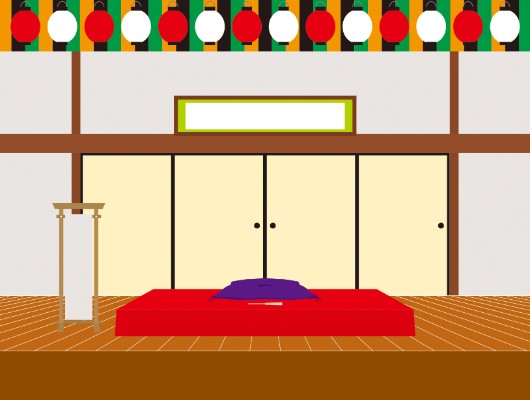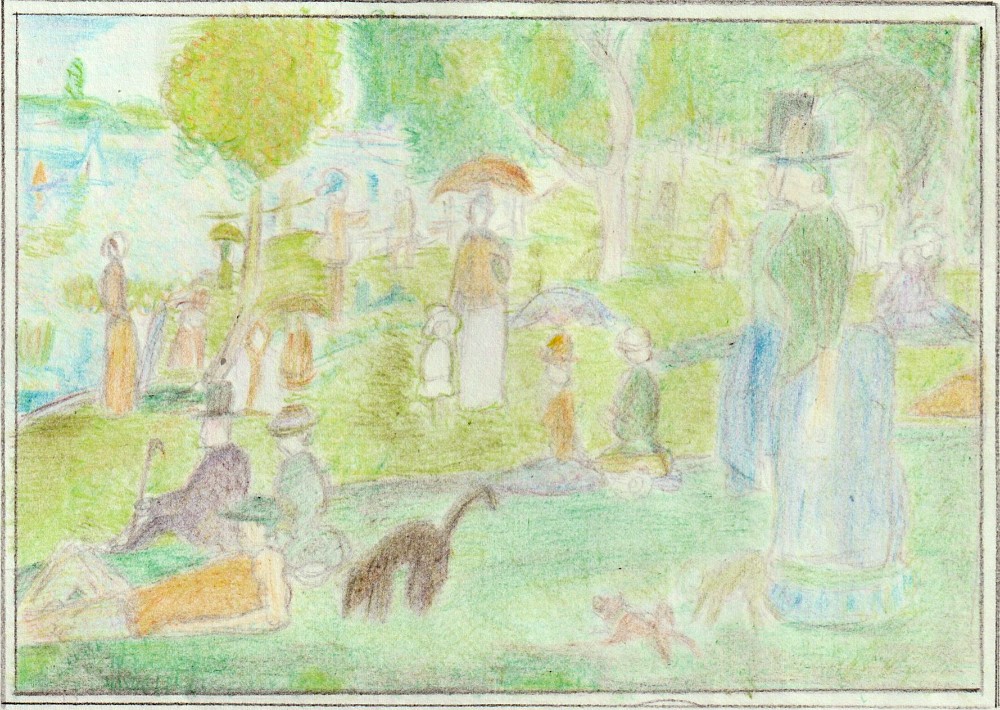2026年2月16日
日本建築-近世寺院
時代背景 破壊の時代 戦国期は読んで字の如く「波乱の時代」でした。戦国大名たちによって繰り広げられる戦火の中で、多くの建物は失われて行きます。そのためこの時代は、新たな建築の生産というよりも、建築の破壊の時代でした。 渦中の寺院 幸か不幸か、当時の寺院も僧兵を構えるなど大名に比肩する勢力を誇っていたため、この争いの渦中に巻き込まれます。たとえば、延暦寺は信長の焼き討ちによって多くの建物が失われ、壊滅状態となりました。また東大寺は、松永久秀や三好三人衆らによる戦闘で戦火を被りました。 復興の時代 しかし16 ...
ReadMore

2026年2月16日
日本建築-外国人居留地
時代背景 日米和親条約 1853年、日本とアメリカとの間で「日米和親条約」が結ばれると、日本近海への西洋船の来訪が増加しました。しかしこの条約にはアメリカ有利の条項*が盛り込まれていたため、日本側の不満は高まって行きます。 アメリカの船が日本の港に寄港する際、日本の法律や手続きを拒否することができました。また、アメリカ船の乗組員が日本人に対して犯罪行為を行った場合でも、アメリカの法律が適用されるという条項が盛り込まれていました。 これに対して、幕府は自国の主権を守るために「異国船打払令」を出しました。この ...
ReadMore

2026年2月16日
日本建築-天守閣
時代背景 大名と張り合う寺院勢力 この時代の有力寺社(東大寺・興福寺・延暦寺など)は、荘園による寺社領の保持・僧兵による武装化によって、絶大な影響力・軍事力を誇っていました。寺社は戦国大名に比肩する一大勢力だったのです。 外来文化による破壊 そんな中、キリスト教の布教や交易のため、ヨーロッパ諸国から日本への来訪が増加します。これによって、多くの文化が持ち込まれました。フランシスコ・ザビエルなどがその例で、新文化の影響を受けた日本人にとっては、既存の世界観や価値観が打ち壊されることになりました。 芽生える火 ...
ReadMore

2026年2月16日
日本建築-密教
時代背景 仏教と政治 この時代、仏教は政治と深い関係にありました*。また、寺院は政治的・官僚的な組織を形成していました*。そのため、寺院が勢力を強めて行くに従い、政治を左右する存在になって行きます。時には天皇位の簒奪さえも企てられました。かくして、政治に対する仏教の影響は看破できないものとなっていくのです。 仏教と政治:仏教伝来の当初、僧侶は天皇家に仕え、国家を守護する役割を担っていました。そのため、天皇家や貴族から保護を受けるようになります。彼ら政治権力者たちの思惑は、仏教を利用して自らの権威や権力を確 ...
ReadMore

2026年2月16日
西洋建築-イタリア・ルネサンス
前の様式 舞台 イタリア・ルネサンスの舞台は、市民階級がいち早く台頭したイタリアの商業都市「フィレンツェ」です。 時代背景 イタリアは、中世において商業や金融の中心地として栄え、豊かな都市国家へと発展しました。このような繁栄の中で、芸術家や学者が集まり、文化的な交流が盛んに行われるようになります。また、イタリアでは古代ローマや古代ギリシャの文化が受け継がれていましたが、ルネサンス期において、これはキリスト教中心の中世思想に対する反発という形をとって現れました。 キリスト教世界のほころび 中世ヨーロッパ社会 ...
ReadMore
前の様式
時代背景
寺院にも自営が求められる
18世紀に入る頃には、幕府や諸藩の財政は悪化し、寺社の造営を行う力を失っていました。そのため、各寺社は自らでの資金調達を迫られます。その方法として、「開帳」「勧化」など、民衆から銭を集めるための行事に力を注ぎます。
行事の集金化
「開帳」は本来、寺社の秘仏などを開扉して、人々と神仏を結縁する宗教行為でした。しかし、財政に困っていた寺院は、「開帳」を堂舎の建立や修理費用のための集金事業として活用するようになったのです。
経済力を身につけた民衆
寺院が疲弊していた一方で、民衆の方の生活はどうだったかというと、戦に駆り出されることもなければ、戦乱によって田畑が荒らされることもない、太平の時代を迎えていました。幕藩体制による支配はあったものの、民衆の生活基盤は安定し、経済的な力をつけていきます。
大衆文化の開花
かくして、民衆の生活に余裕が生まれ始めると、民衆による文化が花開くのでした。特に、「浮世絵」「歌舞伎」「浄瑠璃」「相撲」などが盛り上がりを見せました。
巡礼ブーム
そして、財政難に陥り、資金を求める寺社と、経済力を身につけ、現世利益を求める民衆の思惑が合致し、巡礼や参詣が流行しました。
実は観光目的?
この流行の背景には、もちろん現世利益を求める信仰心もありましたが、実は観光を目的としていたとも考えられています。民衆の移動が制限されていた江戸時代では、民衆が旅行の許可を得ることは容易ではありませんでしたが、寺社の巡礼や参詣を理由にすれば、通行手形の許可がおりやすかったのです。
造形
民衆から資金を集めるには、民衆向けのアプローチが必要で、特に分かりやすい装飾表現が求められました。たとえば、「派手な装飾」「参拝空間の充実」などが挙げられます。
大瀧神社
対象が僧侶から参拝客に変わったことで、観光的な建築が多く作られました。
新勝寺三重塔
この三重塔は、見上げることを意識して作られています。垂木に変えて板軒を使い、その表面には彫刻が施されました。なおかつ、鮮やか色彩で塗り上げられました。
歓喜院聖天堂
構造部材(柱・長押など)には自問彫が施され、木口には「獅子」「麒麟」「猿」「波」などの彫刻が施されています。
妙義神社本殿
深い光沢を放つ漆で壁面が仕上げられ、その上に図様がはめ込まれています。
専修寺如来堂
外に面した建具には、「格子」「障子」などを用いて、明るい空間としました。また、立登せ柱によって、背の高い空間が作り上げられました。
大神山神社奥宮
明るさ・高さは、参拝客の受けを狙ったものなので、参拝空間に工夫が集中しています。
また集客のために、遊興的な寺社も増えていきます。
善光寺
胎内潜り
笠森寺観音堂
四方懸造
負担を減らす工夫
巡礼ブームの反面、民衆にとっては経済的にも時間的にも負担が大きいものでした。そこで、建物だけでなく、機能的な面での工夫も施されます。現地の霊場に訪れるのが困難な人のために、近場に模したミニ霊場が作られたりもしました。
旧正宗寺三匝堂
一つの建物を参詣することで、百ヶ所の札所を廻ったことと同等の価値を持つ「三匝堂」
旧正宗寺三匝堂
参拝客が登り降りするための、二重の螺旋階段が設けられました。これによって、昇る人と降りる人が交差しないようになっています。
参考文献
日本建築史講義|著.海野聡|学芸出版社
建物が語る日本の歴史|著.海野聡|吉川弘文館
建築の歴史|編.西田雅嗣・矢ケ崎善太郎|学芸出版会
日本建築様式史|監修・太田博太郎|美術出版社
次の様式
西洋建築史年表
日本建築史年表

2026年2月16日
西洋絵画−クールベ=マネ
舞台 フランス 第二帝政期、パリの都市改革を始め、社会構造の大きな転換があったフランス。都会人の新しい生活様式などが誕生しました。 背景 産業革命・資本主義の時代 19世紀後半、いよいよ「産業革命」の成果が浸透し始め、かつ「資本主義」の波風が立ち始めました。 近代への突入 「科学技術の飛躍的な進歩」・「都市部への人口集中」・「階級対立の激化」・「西欧の世界進出に伴う異文化交流」などが、人々の日常生活に大きな影響を与えます。 近代絵画の始まり 絵画においては、クールベやマネといった近代絵画の創始者によって、 ...
ReadMore
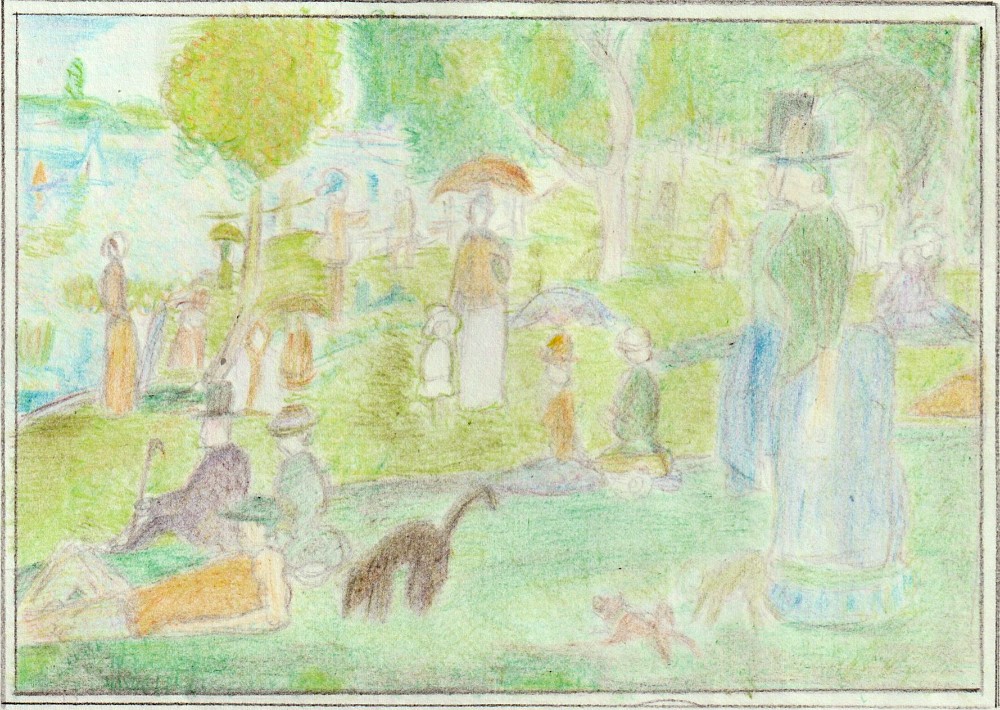
2026年2月16日
西洋絵画−新印象主義
舞台 フランス 印象派に続き、フランスが芸術の中心地として君臨しています。 背景 印象派の乗り越え 時代の寵児であった印象派も、1886年には最後の展覧会を迎え、いよいよ批判と反省の対象として乗り越えられる存在になります。 物の形を犠牲にした印象派 「分析的な手法」を得意とした印象派は、物の「形態感」や「存在感」を失ってしまうという欠点を抱えていました。 新たな活路 印象派の色彩理論に共感しつつもこの弊害を重く見た後代の画家たちは、ここに新たな活路を見出します。 特徴と画家 求めすぎた理想 印象派は「光の ...
ReadMore

2026年2月16日
西洋絵画−オランダ・バロック
舞台 オランダ 16世紀末、「プロテスタント」勢力の強かったフランドル地方の北部にて、「スペイン領からの独立」を果たした新教国、オランダが誕生しました。 背景 イタリアからオランダへ輸入 イタリア起源のバロックは、国境を超えてオランダにも広がりました。 プロテスタントの国 オランダ共和国として独立を果たし、「東インド会社等の国際貿易」により、目覚ましい「経済発展」を遂げたオランダは、その経済力を背景にオランダ独自の「市民文化」を繁栄させていました。 「プロテスタントの国」であったオランダでは、「教会よりも ...
ReadMore

2026年2月16日
絵画−野獣派〈フォーヴィスム〉
著作権に対する配慮:当記事に掲載している模写作品の中には、著作権保護期間中のものが含まれています。そのため、「引用元(元絵)の明記」・「引用の必要性」・「画像は自前で用意すること」・「非営利目的」を徹底した上で、当記事の作成に望んでいます。 舞台 フランス 産業革命以来、急速な進歩によりもたらされた「世界の拡大化」は、多種多様な芸術運動の下、「専門化」・「分化」を押し進めました。そんな中で、新しい視覚体験が模索されます。そして、色彩の面で大きな変革が起きたのはフランスでした。 背景 野獣派結成のきっかけ ...
ReadMore

2026年2月16日
西洋絵画−フランス・ロココ
舞台 フランス 絵画史の中でも、特にロココは時代区分の難しい様式です。そもそもロココとバロックの区分を認めない説もあります。そのため当ブログでは、ロココの特徴が最も顕著に現れている、フランスで展開されたロココのみを取り扱います。 背景 絶対王政に陰りが見え始める 「太陽王ルイ14世」は、神から与えられた王権の行使者としての役割を演じることの出来た「最後の王」でした。 それというのも、1715年に彼が他界すると、その絶対王政にも陰りが見え始め、「貴族等の側近勢力が台頭」して来たからです。 太陽王からの開放 ...
ReadMore