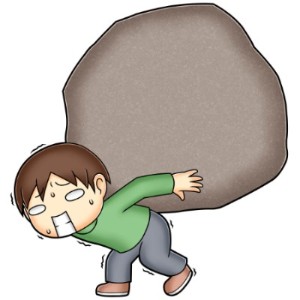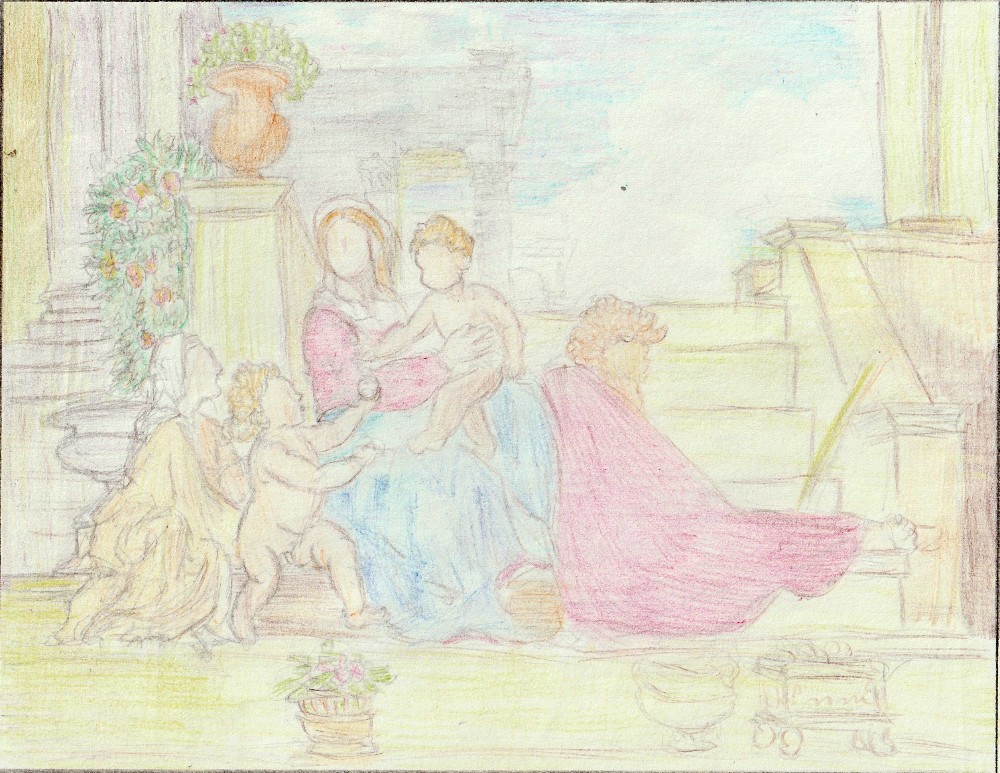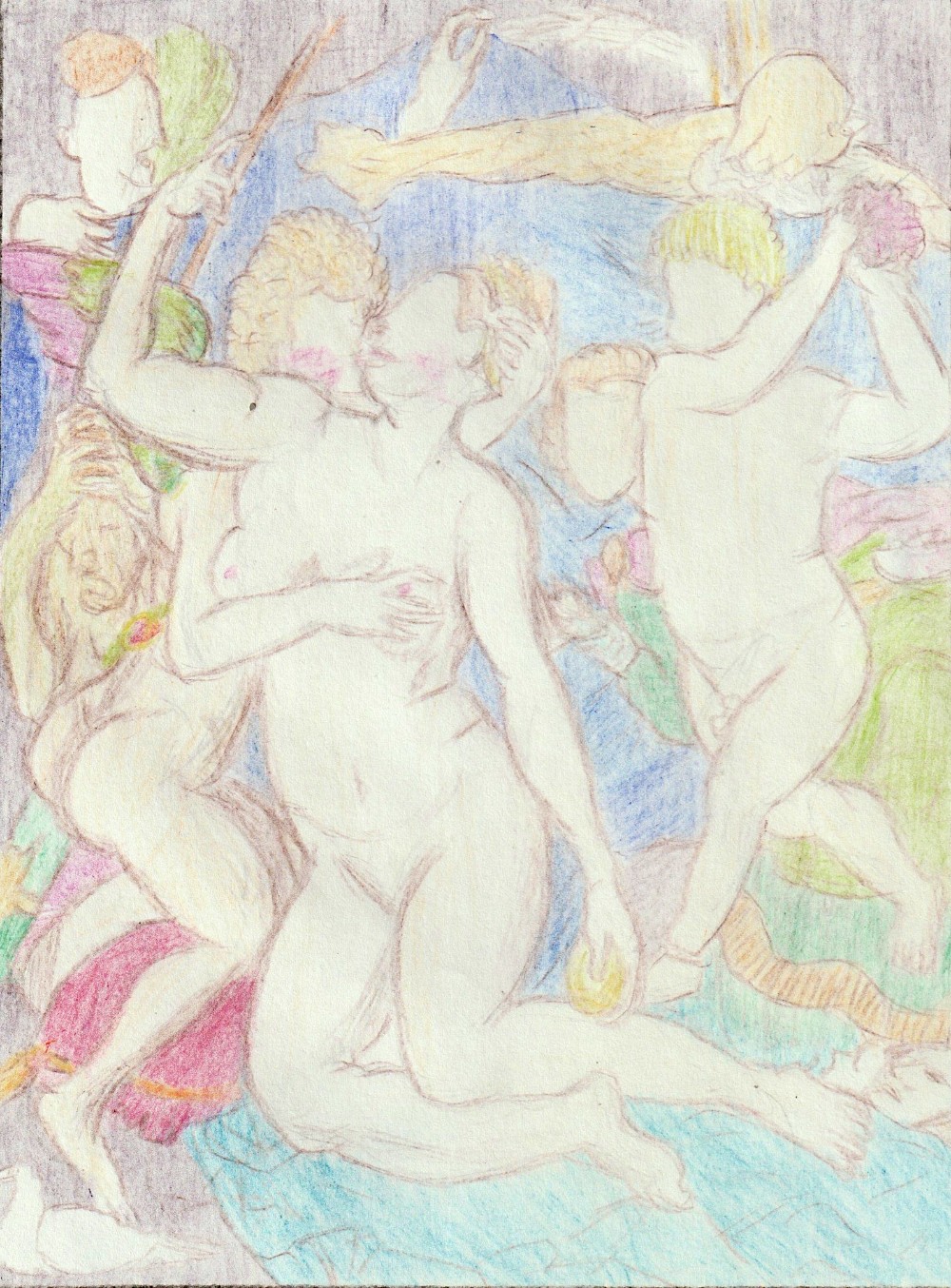2026年2月16日
日本建築-縄文・弥生
時代背景 移動生活 縄文時代は、狩猟・採集の社会です。季節ごとに、動物の移動や植生の変化を追いかけながら、河川の周辺や台地の縁辺部で食べ物を獲得し生活していました。 農耕によって定住が可能に 弥生時代に入り、水稲農耕が広まっていくと、移動生活(狩猟・採集)から定住生活(農耕)へと変化しました。この変化による建築的な変化は、たとえば、場所選びに現れます。これまでは水被害を避けて、台地や丘陵が選ばれていたのに対し、水田に水を引くために水の便が良い場所が好まれるようになったのです。 貧富の差が生まれる 農耕文化 ...
ReadMore

2026年2月16日
日本建築-禅宗様
時代背景 禅宗の伝来 12世紀末、栄西によって日本に禅宗がにもたらされました。禅宗では、これまでの仏教とは教義や儀式も異なるため、僧の生活や建築も変化していきます。 禅宗:仏教の教えを直接実践することで、真実を見出すことを目指します。基本的な修行としては、座禅が挙げられます。 14世紀頃までには、確固たる地位を築き上げることに成功しました。その背景には、得宗政権*や室町幕府が、既存の権門体制に代わる宗教勢力として、禅宗寺院に焦点が当てられたということがあります。得宗政権や室町幕府の支援を得て、禅宗は広く普 ...
ReadMore

2026年2月16日
日本建築-密教
時代背景 仏教と政治 この時代、仏教は政治と深い関係にありました*。また、寺院は政治的・官僚的な組織を形成していました*。そのため、寺院が勢力を強めて行くに従い、政治を左右する存在になって行きます。時には天皇位の簒奪さえも企てられました。かくして、政治に対する仏教の影響は看破できないものとなっていくのです。 仏教と政治:仏教伝来の当初、僧侶は天皇家に仕え、国家を守護する役割を担っていました。そのため、天皇家や貴族から保護を受けるようになります。彼ら政治権力者たちの思惑は、仏教を利用して自らの権威や権力を確 ...
ReadMore

2026年2月16日
西洋建築-ウィーン・ゼツェッション
背景 ハンガリー帝国の情勢 ウィーン・ゼツェッションは、1903年にオーストリア=ハンガリー帝国*の首都ウィーンで結成されたグループです。オーストリア=ハンガリー帝国は複数の民族や国家が集合した多民族国家であったため、深刻な民族問題を抱えていました。 ハンガリー帝国:中央ヨーロッパにかつて存在した帝国。現在のハンガリー、スロバキア、クロアチア、セルビア、ルーマニア、ウクライナ、オーストリアなどの地域を含んでいました。ハプスブルク家の君主がハンガリー王位を兼ねていたことから、オーストリア=ハンガリー帝国とし ...
ReadMore

2026年2月16日
西洋建築-アーツ・アンド・クラフツ
背景 分業体制の始まり 19世紀後半のイギリスでは、産業革命によって工業化が進み、工業製品の需要も高まっていました。それに伴い、機械による大量生産や標準化が進む一方で、工芸品や手仕事の価値は低下していきます。 モリスが立ち上がる 機械的かつ分業的な生産方式を強いられる現状に、一人の男が声を挙げました。我らがW・モリスです。彼は機械による大量生産や標準化に反対し、手仕事や伝統工芸品の価値の再評価を図ったのです。 彼は芸術を労働における人間の悦びの表現であると主張しました。そして物作りの労働が悦びと感じられる ...
ReadMore
前の様式
時代背景
禅宗の伝来
12世紀末、栄西によって日本に禅宗がにもたらされました。禅宗では、これまでの仏教とは教義や儀式も異なるため、僧の生活や建築も変化していきます。
禅宗:仏教の教えを直接実践することで、真実を見出すことを目指します。基本的な修行としては、座禅が挙げられます。
14世紀頃までには、確固たる地位を築き上げることに成功しました。その背景には、得宗政権*や室町幕府が、既存の権門体制に代わる宗教勢力として、禅宗寺院に焦点が当てられたということがあります。得宗政権や室町幕府の支援を得て、禅宗は広く普及していくのです。
得宗政権:北条氏が執権の地位にあった時期の幕府政権。鎌倉幕府の中でも最盛期を迎え、軍事力や政治力を背景に、全国的な支配体制を築きました。
民衆受けはそれほど
ただ、禅宗では瞑想や自制による厳しい修行が求められたため、民衆にとっては少しハードルが高く、身近な存在ではありませんでした。
武家による庇護
その反面、自助努力で生活基盤を確保してきた武士の性分には合っており、そのおかげで武士による保護を得ます。この時代、まさに力を付けつつあった武家の加護を得たことは、禅宗の拡大・全国的な普及に大きく貢献したのです。
自助努力:自分自身で努力して問題を解決し、自己啓発や自己成長を目指すこと
特徴
禅宗の教義や建築様式は、日本に既存するものではなく、新しく中国から輸入されたものでした。また禅宗は、物質的な豊かさや華美さに執着しない、精神的な豊かさを求める教えであり、その精神が建築にも反映されています。
軒に扇垂木を用い、屋根は強い反りを持つ
東大寺鐘楼
扇垂木とは、軒の四隅が扇状になっている形式のことです。
一重裳階
功山寺仏殿
建物自体は一階建てですが、屋根が二つあります。これは厳密にいうと、屋根の下に裳階が付いている状態です。
参考文献
日本建築史講義|著.海野聡|学芸出版社
建物が語る日本の歴史|著.海野聡|吉川弘文館
建築の歴史|編.西田雅嗣・矢ケ崎善太郎|学芸出版会
日本建築様式史|監修・太田博太郎|美術出版社
次の様式
西洋建築史年表
日本建築史年表
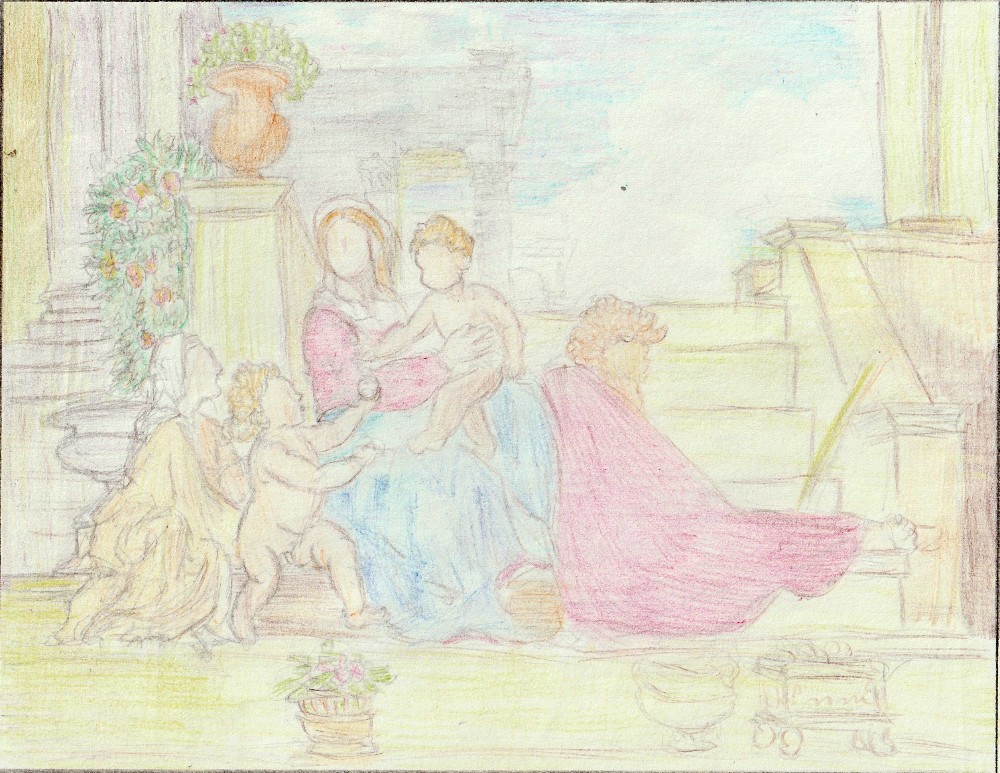
2026年2月16日
西洋絵画−フランス・バロック
舞台 フランス 太陽王ルイ14世が主権権を握る「絶対王政期」のフランスもまた、芸術の舞台となりました。自国の土壌で独自の様式を形成して行きます。 背景 フランスへ輸入 イタリア起源のバロックは、国境を超えてフランスにも広がりました。 伝統を守るフランス しかしフランスでのバロックは、主に前時代様式の否定として展開されて来た各地のバロックと異なり、「古典主義」的な傾向を保ちます。 それというのも、古典尊重のルイ王朝は「古代ローマを美術の範」としたからです。 王立アカデミーの設立 また、王立アカデミーの存在に ...
ReadMore

2026年2月16日
西洋絵画−オランダ・バロック
舞台 オランダ 16世紀末、「プロテスタント」勢力の強かったフランドル地方の北部にて、「スペイン領からの独立」を果たした新教国、オランダが誕生しました。 背景 イタリアからオランダへ輸入 イタリア起源のバロックは、国境を超えてオランダにも広がりました。 プロテスタントの国 オランダ共和国として独立を果たし、「東インド会社等の国際貿易」により、目覚ましい「経済発展」を遂げたオランダは、その経済力を背景にオランダ独自の「市民文化」を繁栄させていました。 「プロテスタントの国」であったオランダでは、「教会よりも ...
ReadMore
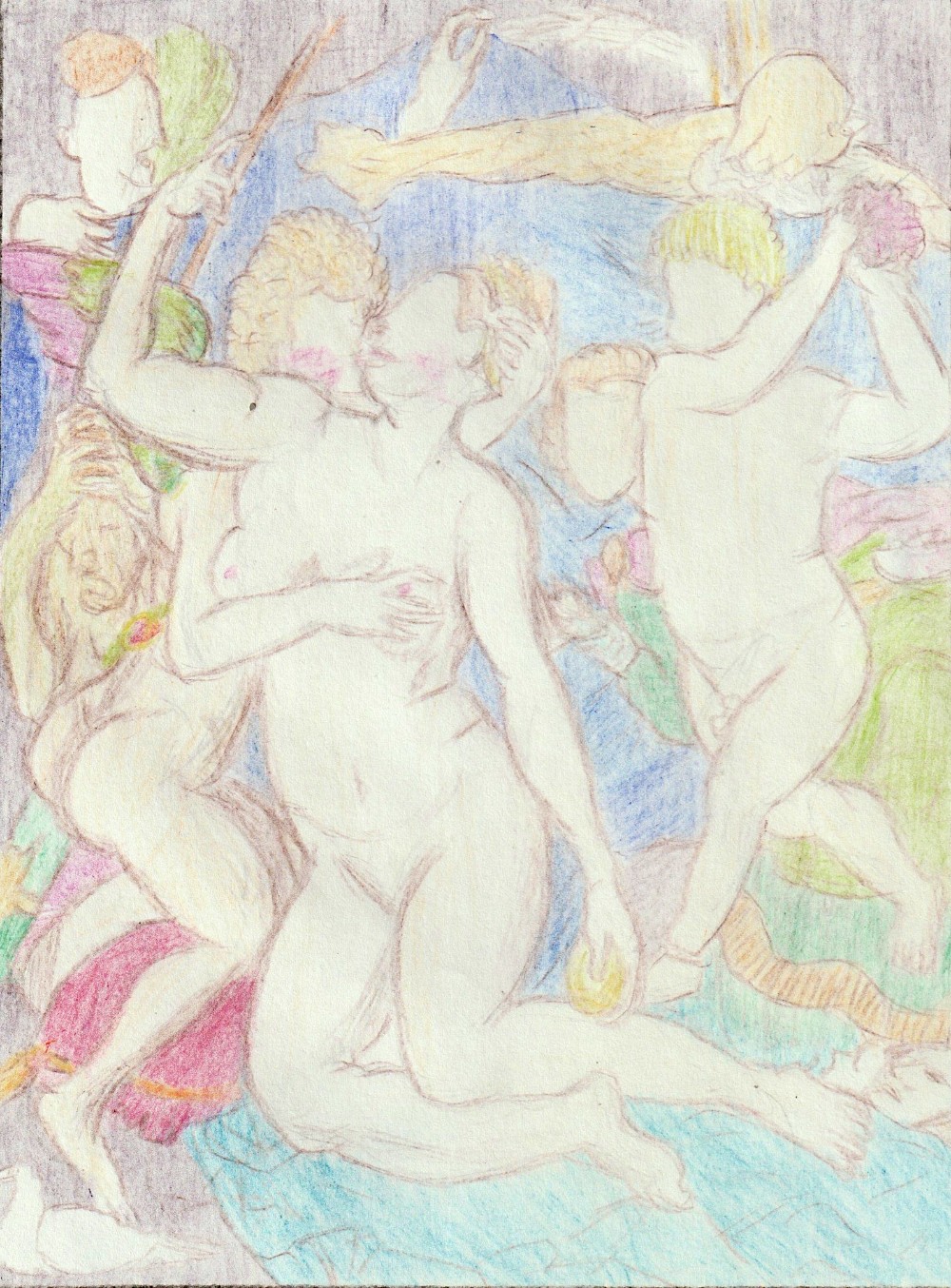
2026年2月16日
西洋絵画−マニエリスム
舞台 国際的な展開 イタリアに端を発したマニエリスムは、16世紀後半には国際的な広がりを見せます。 背景 反宗教改革に乗り出す カトリック教会が「反宗教改革」に乗り出す時代、「神秘的な表現」が求められるようになります。 絵画による奇跡体験 論理を持って「奇跡」を説明することは出来なくても、絵画の世界の中でならそれは可能になるからです。 劇的な表現の追求 それはやがて古典主義の特徴である、「穏やかさ」や「荘厳さ」、「静けさ」や「バランスの重視」に対して、より「魂の根源」に迫る表現に至りました。 ミケランジェ ...
ReadMore

2026年2月16日
西洋絵画−印象派
舞台 フランス フランス美術は西洋絵画史の主要舞台の座を確立しました。イギリス風景画の伝統もスペイン画家ゴヤの系譜もフランスに吸収され、オランダ画家ゴッホもこの地での修行を得て覚醒しました。 背景 印象派展の開催 1874年、モネ・ルノワール・セザンヌ・ドガ・ピサロらによって、展覧会が開かれました。 彼らの作品に共通して見られる「スケッチ的な作風」から、この展覧会に集まった彼らは総称して、「印象派」と命名されることになります。 多様性に満ちた印象派グループ しかし実際のところ、彼らには明確な意味での共有さ ...
ReadMore

2026年2月16日
西洋絵画−イタリア・バロック
舞台 イタリア 16世紀後半のイタリア、おおよそ芸術活動の低迷期に入っていました。しかし、カラヴァッジョの活躍によって、ローマで新たな盛り上がりを見せます。その後、カラヴァッジョ様式は国際的な広がりを見せました。(本記事では、イタリアに比較的近しい展開を見せたフランドル・スペインも一緒に取り上げます) 背景 宗教改革に対抗するカトリック教会 カトリック協会の免罪符を直接のきっかけに、「宗教改革」が勃発。離れていった信者の心を取り戻すため、カトリック教会は「反宗教改革」に乗り出しました。 分かり易さを武器に ...
ReadMore